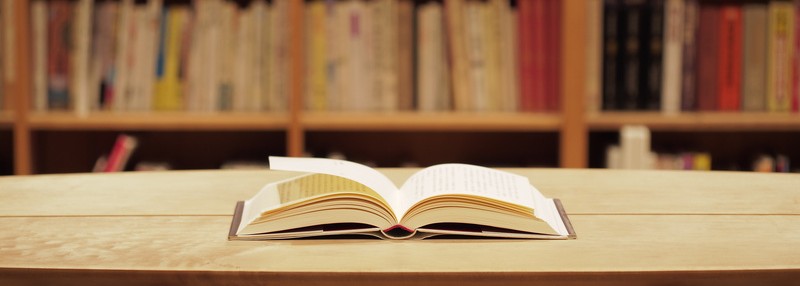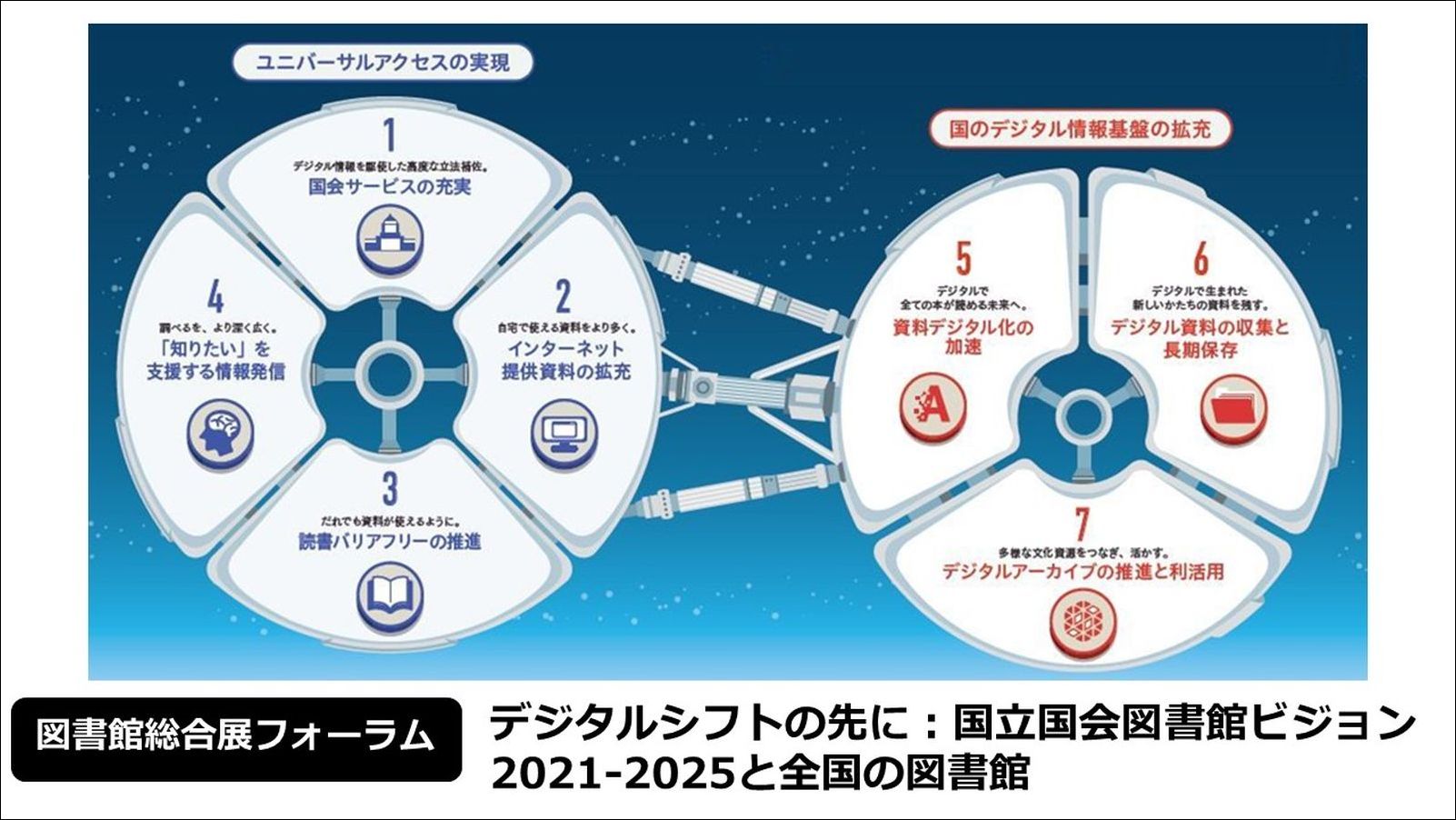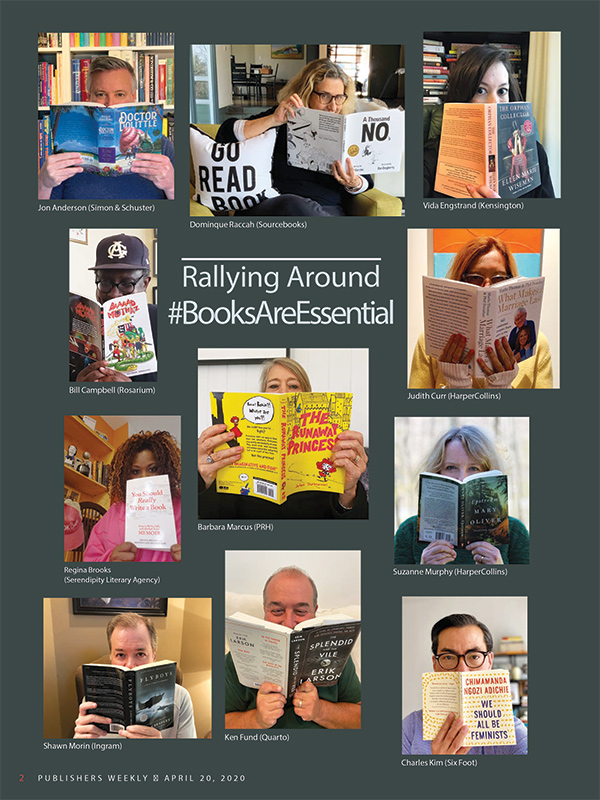読む、書く行為のデジタル化、したがって液晶画面化が進行している。この変化は果たして、人間の脳の発達や働きにどのような変化を生むのか? 『デジタルで読む脳 X 紙の本で読む脳』はそうした疑問に答えようとする啓発の書。同時に、デジタル時代に「深い読み」が絶滅危惧種にならなくするにはどうしたよいのか、考え抜いた警世の書。
■ディスレクシア
著者メアリアン・ウルフは認知神経科学、発達心理学の専門家。とりわけディスレクシア(識字障害)の研究で著名な学者。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院・教育情報学部の「ディスレクシア・多様な学習者・社会的公正センター」所長です。 Continue reading