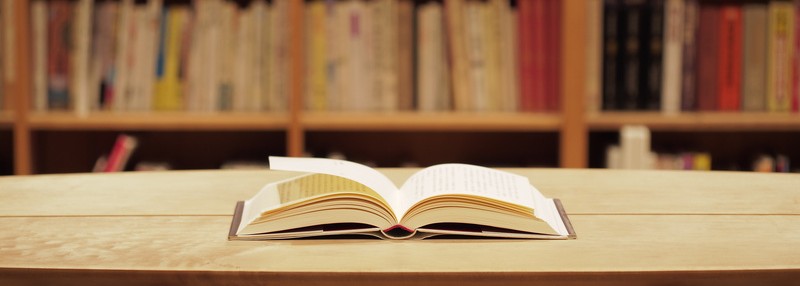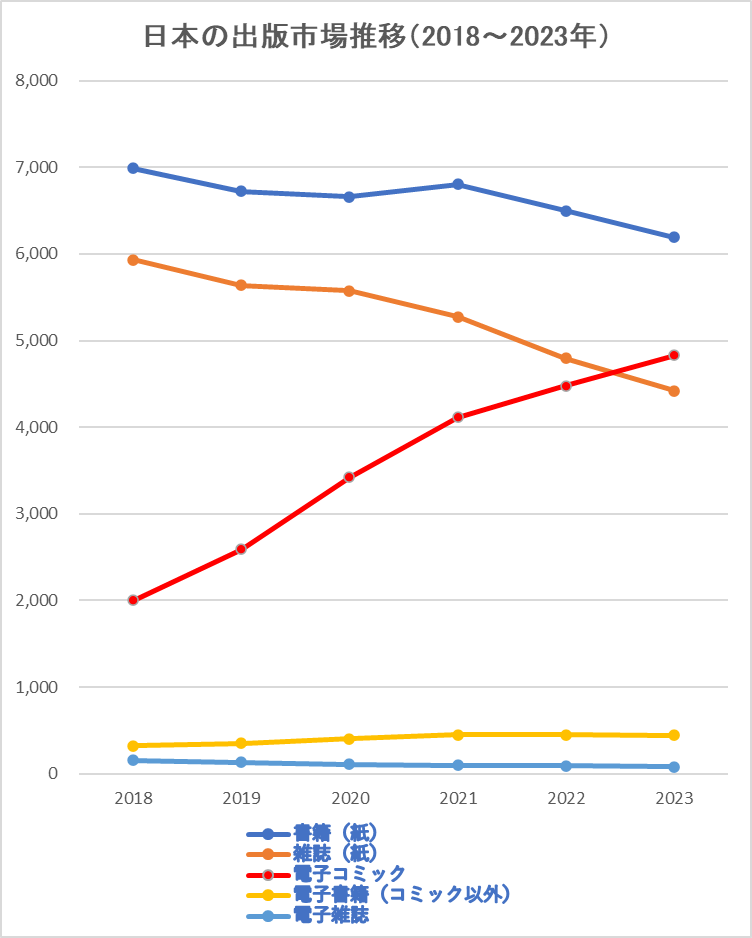◎これはクリップ集です◎
これまで「読書離れ」は大人の問題とされ、日本の義務教育課程は読書習慣をよく育ててきました。しかし、その状況に変化が訪れています。動画とAIが日本の子どもたちの学習環境を揺るがしています。
1.「読書が好き」の低下が示す基盤の揺らぎ
全国学校図書館協議会の「学校読書調査2025」は、日本の読書環境が明確な転換点にあることを示しています。不読率は小中高すべてで上昇し、とりわけ高校生では半数超が月に一冊も本を読まない状況。もっと注目すべきは、単なる冊数の減少ではなく、「全国学⼒・学習状況調査」の調査での「読書が好き」という意識や読書時間そのものが低下している点(下記知恵クリップ)です。言語を通じて世界を理解する力の基盤が、揺らごうとしています。
●読書は好きですか
・小学生の「当てはまる」の回答率
令和7年 36.6%
令和4年 42.1%
平成31年 44.4%
平成29年 49.1%
平成28年 49.5%
平成27年 49.0%
・中学生の「当てはまる」の回答率
令和7年 30.4%
令和4年 38.0%
平成31年 39.1%
平成29年 46.2%
平成28年 46.6%
平成27年 45.0%
全国学力・学習状況調査 「結果読書は好きですか」