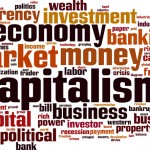※これは村上龍事務所が発行するメルマガ、「JMM [Japan Mail Media](サイト: http://ryumurakami.com/jmm/ )」での人気連載、『from 911/USAレポート』の第706回配信記事全文です。
執筆者の冷泉彰彦氏、またJMM様のご了解をいただき、全文転載させていただいています。
人類の文明の実験場であり、また多様な社会が衝突と共存の歴史を作ってきた欧州では、それぞれの時代において「衰退に瀕した国家」が存在していました。そのような国家のことを、同時代のジャーナリズムや後世の史家は「欧州の病人」と呼んで批判をするのが通例となっています。古くは19世紀末から20世紀初頭のオスマントルコや、オーストリア帝国がそうであり、特に有名なのは1970年代の英国です。
日本では、この英国については、「欧州の病人である英国」という表現を少し変えて、日本独特の形容として「英国病」という言い方がされていました。人類に先駆けて第一次産業革命を実現し、日の沈むことはないという大英帝国を創り上げた栄華は過去のものとなり、人材育成のミスマッチなどから競争力を喪失する一方で、組合主導の高コスト社会が動きが取れなくなっていたのでした。
明治維新以来、その英国を複雑な思いと共に目標に戴いてきた日本としては、そのような英国の衰退は「英国に特有の問題があるからだ」という印象が強かったのでしょう。また、当時は飛ぶ鳥を落とすような経済成長を続け、二度の石油ショックも技術力などで乗り切っていた日本としては、英国への落胆と蔑視の感情も交じる微妙な言い方として「英国病」という表現は、どこかで納得がされたものです。
その英国は、サッチャーによる痛みを伴う改革を経て高コスト体質を清算、そして90年代のグルーバリズムに乗る中で、現在は自他共に「欧州の病人」という形容は返上しています。その一方で、2015年の日本は、70年代の英国がそうであったように「病」に臥せりがちの経済に苦しんでいます。
経済の国際比較の指標として、「一人あたりGDP」というのは全てを語るものではないかもしれません。ですが、「たかがGDP、されどGDP」ということで、この「一人あたり」を見てみると、時代の推移は歴然としています。
例えば、日本政府(内閣府)は12月25日に、2014年の日本の1人当たり名目GDPが36200ドルであったと発表しています。これは、前年比6%減であり、OECDに加盟する34か国のうち上から20番目(前年は19位から1位ダウン)でした。これは、「統計が確認できる1970年以降」では最も低い順位だそうです。
この政府発表には円ベースの数字もあり、こちらは前年度比1・7%増の385万3000円です。3万6千ドルを「1ドル=121円」で換算すると4万ドルを大きく超えるはずですが、生産額の元が円ベースのものと、ドルベースのものがある中での計算ですから、そう単純ではありません。
一方でIMFが毎年出している統計では、2014年の日本の1人当たりGDPは、36221ドルで、この政府数字とほぼ一致しています。但し、IMFは187カ国中のランキングとして出しているために、日本は27位とランクを下げています。
そのIMFのランキングの上位はベネルクスや北欧などの小規模国と産油国が占めていますが、大国の中でも米国(54370ドル、11位)、カナダ(50304ドル、15位)、ドイツ(47773ドル、17位)には大きく離されたばかりか、「英国病」とかつては見下していた英国(45729ドル、19位)にも、そして「長期バカンスを取る国」と生産性の低さを批判していた対象のフランス(44331ドル、20位)にも抜かれているのです。それどころか「幸福度だけ高いが経済はダメ」という印象で見ていたイタリア(35334ドル、28位)が僅差で迫ってきているのです。
同じアジアの中では、かつては「アジアの4小龍」とか「NIES」などと勝手に命名していたシンガポールは56286ドル(9位)で日本の155%、香港も40032ドル(25位)で日本の110%となっています。
更に言えば、「4万ドル以上」のクラブは香港(25位)までであり、日本の属する「3万ドル台」のグループに入っているのは、「イスラエル、日本、イタリア、スペイン」の4カ国で、そのすぐ下には韓国が迫っている、そんな構図になっています。
かつて、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」などと賞賛と畏怖の対象となり、事実この一人当たりGDPでは米国を抜いて、人口2千万以上の大国の中では堂々のトップに君臨していた「経済大国」の面影はどこにもありません。
これは自他共にある種の「病」であると認めなくてはならない事態です。1989年の「バブル崩壊」によって金融危機が引き起こされ、経済が大きく痛手を被ったということに直接の理由を求めることは、もはや何も説明していないのと同じです。この急速な衰退は、事故や怪我といった外的要因に基づくものではなく、内発的な「病気」であり、その診断が急がれると思うのです。
その「日本の病気」つまり「日本病」とは何なのでしょうか? 少々長い前口上となりましたが、年末年始の議論の材料にしていただければ幸いです。
(1)コミュニケーションと言語の特殊性
現在、世界のビジネスの現場におけるコミュニケーションは、英語が基本になっています。特に国境を超えるビジネスはそうですし、各地域のローカルのビジネスであっても上場をしている場合は株主や当局とのコミュニケーションは英語が中心ですし、契約書や紛争処理においても英語が中心です。
また、コンピュータの分野、機械工学、薬学、化学、といったテクノロジーに関するビジネス、そして金融というビジネスにおいても英語が標準語です。英語が母語でない、大陸ヨーロッパにおいても、英語を共通語として使用しています。アジアにおいても、ビジネスにおいて成功しているシンガポール、香港では英語がビジネスの重要なインフラになっています。
ですから、日本のビジネスの世界において「余り英語が通じない」というのは、それだけで大きなハンデとなります。これに加えて、日本語には顕著な特殊性があります。それは、「高コンテキスト」言語であるということと、「上下関係を規定する敬語表現」に縛られているという問題です。
まず「暗黙の了解」というのは、どういうことかというと、言語に現れない「暗黙の共通理解、情報の共有」というのがコミュニケーションの前提になっている、そのような行動様式であるわけです。「空気」という言い方を良くしますが、とにかく言外の「共通認識」が確認できればその部分は言葉にしないし、言葉にしないことで認識の共有化が強く確認できる、そのようなコミュニケーション様式が日本語には濃厚です。
このことは「個人的な信頼関係があるか、ありそうなこと」は「基本的に言葉にしない」という態度として、日本語の表現を作っています。それは書き言葉でもそうですが、話し言葉でも顕著です。悪いことに、そのような「面と向かって、あるいは共通の場にいる」という物理的な対面を前提にして、「物理的に対面しているが言語化はしない」という経験が「最も濃厚なコミュニケーション」であり、それはエモーションの濃さという意味でも、ファクトの確認という意味でも、コマンドの有効性という意味でもそうなります。
これは多くの局面において「メールで済む」話を「対面コミュニケーション」にしないと「いけない」という行動様式につながっています。ですから、日本の会社は社内においては会議を好み、日本の会社の営業は「相手との個人的な信頼関係」を作るとして「訪問して対面のコミュニケーション」を極めて重視します。
その結果として、社内における意思決定や手続きの変更、社外を相手にした受注やサービスの提供ということが、ものすごい時間と手間を要することになります。少しでも例外であったり、重要であったりするケースは、言語をメールで届けるだけではダメで、対面コミュニケーションを行って、言外の領域でも相互に納得をしないと組織も人も動かないようにできているからです。
(2)上下関係のヒエラルキー
ここからは言語に加えて、組織論も重なっていきますが、もう一つ、日本語でのコミュニケーションの特質は、上下関係を規定する敬語という問題を伴っているということです。そのために、管理監督者は指揮命令の対象に対して、人格的に優位に立っていると錯覚して、横柄なコミュニケーションが許されていることがほとんどです。そのために、様々な非効率が発生しています。
一つには、儀式的なヒエラルキーの確認に、個人の自尊心の満足感を刺激する形で、昇進昇格人事が行われているということです。管理監督というのは、未来の未経験の事態に対してチームのパフォーマンスを最大にして問題解決を行うためのリーダーシップであるべきですが、得てして「過去の功績の論功行賞としての昇格」が横行するために、不適格者、能力欠格者が管理監督の権限を与えられて、人格的に優位に立ったという錯覚を前提とした権力行使を行うことが多くあるわけです。そのために問題が解決できず、ビジネスチャンスが生かせないという膨大なロスが日本経済の足を引っ張っています。
これは組織における管理監督者の配置の問題であり、その背景にある「年功序列」とか「ゼネラリスト育成のための人事異動」などが問題の本質にはありますが、更にコミュニケーションにおけるヒエラルキー文化が重なることが問題を複雑にしていると言えます。
もう一つは、得てして現場が持っている「最先端の情報」「危機の発端となるマイナス情報」が決定権限のある人間に上がっていかないという問題。更には、問題が生じた際に、迅速に「対策の立案と実施」に進む前に「責任者の謝罪という儀式」に時間を取られるという問題があります。
個々のコミュニケーションの局面だけでなく、産業間や、一つの産業内の機能と機能の間にも暗黙のヒエラルキーが存在しています。親会社と子会社、グループの中核企業と新興企業、伝統と格式のある会社の信用、ベンチャーにおける資金調達の困難など、意味のないヒエラルキーが多く存在することで、様々な非効率が発生しています。
(3)東京一極集中は何故ダメなのか?
こうした問題を象徴しているのが「東京一極集中」です。東京への一極集中がどうしていけないのかというと、地方が衰退するとか、東京の住環境が悪化する、あるいは災害時にバックアップが無いという問題が指摘されます。ですが、そうした表面的な問題以上に、もっと本質的な問題、つまり「東京という街の抱えた病=東京病」というものが指摘できるように思います。
それは、一つにはここまで議論したような「高コンテキストで非効率な対面型コミュニケーション」の束縛ということがあります。多くの機能が東京に集まっているのは、このためであり、そうした「対面型」を要求すればするほど、ビジネスの手順は非効率になって行く、東京というのはそのような街であるのです。
もう一つは、東京は「ヒエラルキー文化にまみれた街」だということです。そこには東京が威張っているとか、中央政府が地方を見下しているという問題もありますが、もっと罪深いのは「東京というのは明治以来の欧米への劣等意識にまみれた街」だということです。
そこで起きるのは、「地方<東京<欧米」という歪んだヒエラルキー意識であり、また、地方が海外の知見なり市場なりと結びつくには、「一旦東京を経由しなくてはならない」という非効率を産んでいるとも言えます。この2つの問題、つまり「対面型の非生産的なコミュニケーションを象徴する街」であり「地方に対して君臨し、欧米に対して拝跪するという巨大な田舎根性の街」というところ、そこに東京一極集中の最大の問題があるように思います。
この年の瀬に至って、問題となっている東芝、キリンの経営こそ、その典型例であると言えます。東芝は、米国の原発事業を買収した後の経営に難渋し、しかも問題の本質に直面することから逃げて不正な方法で会社の体面を取り繕うとしたことから更に大きなトラブルへと陥っています。キリンも、ブラジルで買収した事業の経営悪化をグループ全体の問題として正視するのが数期遅れたことが問題を深刻にしていますが、いずれも「東京経由の国際化」の底の浅さを示す良い例だと思います。
(4)産業構造が高付加価値型になっていない
長い間、日本は自他共に認める先進国だと思ってきました。ですが、一人当たりGDPの「4万ドルクラブ」から脱落した現在、その地位はかなり怪しくなっています。それは、ここまで議論したような文化的な効率の悪さということもありますが、それ以前の問題として、現代の先進国に必要な「高付加価値産業」へのシフトができていないというのが、最大の問題です。
例えば輸送用機器では、船舶から自動車・鉄道車両といった段階では、今でも競争力がありますが、付加価値という点で更に一段上の「宇宙航空」に関する技術力では、どう考えても最先端に届いていません。
また、製薬の分野では最先端に必死になって「しがみついて」いるものの、欧米との格差は大きなものがあります。
最大の問題はエレクトロニクスとコンピュータ関連の技術の分野です。この領域では、ハードからソフトへという大きな潮流に、日本は全く乗ることができませんでした。亡くなったスティーブ・ジョブズは、いつも「自分はソニー製のビデオカメラを偏愛していた」としながらも「そのソニーを含めた日本のエレクトロニクス産業は死んだクジラが砂浜に打ち上げられたような状態だ」という厳しい指摘もしていました。
原因はハッキリしています。コンピュータ科学の分野は「余りにも高い専門性が要求される」ので、日本の大企業の中枢を担う「幹部候補のキャリアパス」にはならなかったのです。そのために、「コンピュータのソフトウェアの専門家」は、特殊な専門職種だということになり、社会的な尊敬と、必要な報酬を与えられなかったのです。優秀な若者がそこに集まることはなく、気がついた時点では深刻なまでの遅れを取っており、しかもそのことの深刻さを認識する能力も喪失していたのです。
今から考えれば、2000年代前半の「デジタル三種の神器」というのは、まるで日本のエレクトロニクス産業の「破滅の前の幻」であったと言えます。今は、スマホの高度化によってデジカメというカテゴリは危機に瀕していますが、そのことよりも、デジカメというデバイスを販売するというビジネスモデルよりも、デジタル写真を道具としてネット環境上に巨大なコミュニケーションのプラットフォームを築くというSNSというビジネスモデルが巨大な産業になって行ったということです。
そのような利用者の心理を見ながら、ネット上のサービスを拡大していくビジネスモデルは日本ではなかなか生まれませんでした。そして気がついた時には、薄型ディスプレイも、デジタルカメラもコモディティ化するか消滅の危機に瀕しています。また、BDストレージに至っては、世界市場でのニーズもそれほど出ませんでした。
(5)苦手でも金融をやるしかない
日本人は金融が苦手だとよく言われます。例えば、「リスクを取らないというリスク」という概念を理解しないとか、「ハイ・リスクからロー・リスクの各種の商品を組み合わせたポートフォリオ」の概念が分からないということがよく言われます。売却益や配当収入を「不労所得」だとして蔑視するカルチャーもあります。
ですが、自分が得意だと思っていた「モノづくり」がもはや大きなカネを産まなくなって来ている21世紀の現在、これだけの高度な教育を受けた人口を抱えた国としては、金融を産業として育てていくことは必要と思います。それ以前の問題として、多くの産業化プロジェクトが「石油ショック以来の資金不足」で潰れていったことを考えると、金融の技術力の底上げを図る中で、世界からカネを集めてくることは、今後の産業構想転換のためにも必要と思われます。
それこそ「大学」に瀕していた英国は、金融に関する大胆な規制緩和を行いました。それは、一旦はロンドンがウォール街の軍門に降るということを意味しましたが、時間とともにノウハウと人材が定着する中で、今では、潰れたリーマンの優良部分をバークレイが買うなど、米系に伍した戦いができるようになっています。そして、英国は日本よりはるか上位の「一人当たりGDP」を謳歌する中で、その相当な部分を金融業とその派生で補っているのです。
(6)無駄だらけの教育システム
もしかしたら、「日本病」の最大の問題は教育かもしれません。とにかく、中学なら中学、高校なら高校の教育内容について「その内容それ自体が若者の知性を鍛え、知識として蓄積される」ようになっていないのです。中等教育というものは、それ自体の意味もなければ、高等教育への接続にもなっていない、そうではなくて、高等教育機関である大学には「入学試験」というものがあって、その試験に合格することが下位の学校の唯一のテーマとなっているのです。
そこで高校でその受験勉強を教えてくれれば良いのですが、多くの、特に都市部の高校では十分な指導ができないので、塾や受験産業が必要とされるという奇怪な状況となっています。つまり中等教育までの段階では、「教わったことはそれ自体に意味はなく、次の段階の学校の入試に受かるかどうかという一点のみの関心と利害が学習の目的と動機」になっていて、しかもその目標達成には「学校以外の塾に行かねばならない」という非効率になっているのです。
更に大学での履修内容も、理系を除いては「企業や官庁で必要とされているスキルや知識」とは異なっており、就職後に「学び直し」を強制されるのです。その一方で、大学以下の学習内容は必ずしも高度ではありません。高校の時点、すなわち大学入試の出題範囲は狭く、微分方程式もなければ、関数電卓を使った高度な数値の操作も要求されません。
一部のエリート候補向けとされる「中学入試」では、xやyを使った方程式も禁止されるという馬鹿げた規制の元での「頭の体操」を強いられるという奇怪な現象すらあります。要するに形式的で、正確性ばかりを要求されるが、内容はちっとも高度ではないというバカバカしい教育が「受験地獄」として、意味のない労力の浪費を若者に強いており、しかもそれは社会に出たら「使えない」という無駄なことになっているわけです。その壮大な無駄の積み重ねが日本の競争力喪失の大きな理由の一つだと思います。
私は先日、日本に一時帰国した折に、東京の水道橋駅で大勢の女子高校生が電車に乗ってくるのに遭遇しました。制服と校章から、東京大学の多くの合格者を出している日本版の「プレップスクール」と分かりましたが、彼女らが電車の中で一心不乱になって見ているのが、「文科省検定済みの生物2の教科書」だったのです。私はそのことに愕然としました。
生物2を履修しているというのは、恐らくは理系志望で東京大学の理科科類に入学していく女性たちなのでしょうが、16歳から17歳の柔軟な頭脳の時期に、最先端の学術論文や、サイエンス誌、あるいは問題提起型の科学哲学や科学と社会の関係の専門書などではなく「生物2」の教科書を必死になって勉強している、それは定期試験のためなのでしょうが、そのレベルの低さ、そして何も言わずに暗記をしているという作業の低付加価値に愕然としたのです。そんなことをやっている場合ではない、多くのアジアや欧米の同年代の女性たちは、仮に基礎能力が優秀であれば、もっと高度なことをやっているのです。
日本の教育システムが時代遅れであり、しかも無駄だらけで「易しすぎる」ということ、そのことも今後の国際競争力維持においては問題視していかねばなりません。
そんなわけで、「日本病」というのは、どうやら複合的な疾病のようです。日本のカルチャーが持っている特質は、中付加価値製品の設計と製造には適していたのかもしれませんが、高付価値型のビジネスのためには、むしろ弊害となっていると考えれば、そうした問題点の多くを日本特有の「病」であるとして、克服をしていくことは急務ではないでしょうか。
いずれにしても、本稿は、年末年始の皆さまの議論の材料にしていただければと思って書いております。かなり荒削りな部分もあるのですが、それは「一人当たりGDP4万ドルのクラブ」から叩きだされ、英国にもフランスにも抜かれ、今は「3万ドルグループ」に留まることができるかの瀬戸際で、イタリアにも抜かれそうだということのショック、そして、日本国内の報道ではそんなに「ショックが感じられていない」ということへの二重のショックから、どうしても荒っぽくなってしまったのかもしれません。
いずれにしても、この「診断」はあくまで「叩き台」として、具体的な改革へと考え方を練りあげて行きたいと思います。末筆とはなりますが、読者の皆さまにはどうぞ良い年をお迎えください。
------------------------------------------------------------------
冷泉彰彦(れいぜい・あきひこ)
作家(米国ニュージャージー州在住)1959年東京生まれ。東京大学文学部、コロンビア大学大学院(修士)卒。著書に『911 セプテンバーイレブンス』『メジャーリーグの愛され方』『「関係の空気」「場の空気」』『アメリカは本当に「貧困大国」なのか?』『チェンジはどこへ消えたか~オーラをなくしたオバマの試練』。訳書に『チャター』がある。 最新作は『場違いな人~「空気」と「目線」に悩まないコミュニケーション』(大和書房)。またNHKBS『クールジャパン』の準レギュラーを務める。