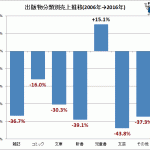読む、書く行為のデジタル化、したがって液晶画面化が進行している。この変化は果たして、人間の脳の発達や働きにどのような変化を生むのか? 『デジタルで読む脳 X 紙の本で読む脳』はそうした疑問に答えようとする啓発の書。同時に、デジタル時代に「深い読み」が絶滅危惧種にならなくするにはどうしたよいのか、考え抜いた警世の書。
■ディスレクシア
著者メアリアン・ウルフは認知神経科学、発達心理学の専門家。とりわけディスレクシア(識字障害)の研究で著名な学者。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院・教育情報学部の「ディスレクシア・多様な学習者・社会的公正センター」所長です。
ディスレクシアを冠する、このセンターこそ、「脳が本を読む」とはどういう営為なのかを研究するのに、そして本書を書くのにふさわしい場所だったといえそうです。
・著者 メアリアン・ウルフ (Maryanne Wolf)

「識字障害(ディスクレシア)」とは、知的機能の発達の遅れや視覚障害がないにもかかわらず、読むことに著しい困難を抱える症状です。
軽度の識字障害なら社会に広く分布しています。有名どころ、現代人ならトム・クルーズ、オーランド・ブルーム、キアヌ・リーブス、ジョン・レノンなど。歴史上の人物ならレオナルド・ダ・ヴィンチ、グラハム・ベル、エジソン、オーギュスト・ロダン、アントニオ・ガウディ、アインシュタインなど。
ウルフも実は、自分の子供がディスレクシアで、家系にもディスクレシアがあったことから、「脳が本を読む」とは、というテーマにアカデミックにとりくんでいました。
したがって識字障害、要は「読めない」側から、「文字列を読む」とは、「意味を読みとる」とはどういうことなのかを、ウルフは追求したのです。「読字」のさいに人間の脳で何が起きているかを、脳神経学の方法論で解明していったのです。
「脳が本を読む」とは、視覚的に受容した文字を脳内で音に変換し、次に単語や文節の形から直接意味を理解するなど、脳神経での複雑な処理、多様な行程を経て実現されている知的活動です。そういった一連の脳内挙動のどこかに,何らかの障害が生じていると考えられているのがディスレクシアだったわけです。
■「読む」ためには新しい脳回路が必要
脳神経学の方法論で「本を読む」とは、を研究した結果、わかったこと。
1.人間には、言葉を発する能力のための脳回路は先天的に備わっているが、読字能力のための脳回路を最初から備えてはいない。ある年齢になれば自然と読めるようになったりはしない。
2.読字能力を獲得する(読字能力のための脳回路を形成する)際、脳内で、視覚、言語、認知を担う領域が、運動と感情を担う領域と連携している。「読む」という営為に密接に関係している、身体性に十分留意する必要がある。
3.脳には可塑性がある。つまり成長する環境に応じて、読字能力は発達する。だから読字能力の高低は、何を読むか、どう読むか、どう形成されるか(教育の手法)にかかっている。
4.「深い読み(著者の知恵を超えて自分自身の知恵を発見する「読み」)」は共感する能力や他人の視点取得に大きく関わっており、民主主義社会の持続可能性に寄与している、といえる。
実はこの本には前著、『プルーストとイカ(原著2007年)』があります。副題が「読書は脳をどのように変えるのか?」でした。ここでプルーストは著者ウルフが唱える「深い読み」の象徴。プルーストが書いた『失われた時を求めて』は、人間の内面の「意識の流れ」を綿密に追うことにより従来の小説概念を大きく変革したとされる作品です。そのプルーストは、読書が人間社会に貴重なのは、それが「著者の知恵を超えて自分自身の知恵を発見する」行為だからだとしたのでした。
そして「イカ」。1950年代の脳神経学者たちは、臆病でいながら器用さも備えているイカの、長い中枢軸策を研究対象として、神経細胞がどのように発火、つまり電気的な興奮で情報を伝達しあうのか、解明しようとしていました。つまり「プルーストとイカ」は、「深い読みと脳神経学」です。
ちなみに脳の原理を「神経回路」の視点から解説した本としては『脳と情報』があります。
『プルーストとイカ』の英語原著が刊行されたのが2007年。この年、米国にAppleのiPhoneが登場します。そして、電子書籍ストア「Kindle Store」とともに、初代の「Kindle」がAmazonから登場しました。
当時、著者ウルフは紙の本と電子書籍、あるいは印刷ベースの「読み」とデジタルベースの「読み」について、「頭の切り替えで乗り越えられるのではないか」と考えていました。そこから10年ほど経ったところで、「読字」が、つまり「読む」ための新しい脳回路の生成そのものが、デジタル化が進展する社会の中でリスクにさらされていると感じました。
本書(原著2018年)で指摘したのは、「適切な教育的指導がなければ、デジタル情報には弊害がある(=深く考えることができなくなる)」こと。ただし、デジタルの有用性は認めており、印刷ベースの「読み」とデジタルベースの「読み」、双方活用できる「バイリテラシー脳を育成すべき」だと主張しています。
■わかったことからの提言
デジタル化が進む現代。社会に、「深い読み」を再生産していく、その方法論に対して意識的でないと人間の文明が後退してしまわないか、著者は危惧しています。その問題意識から本書ではいくつかの提案が行われています。
詳細はもちろん、本書にあたっていただくしかありません。が、いくつかのポイント拾い上げて、あなたがこの本を読むべき理由を見つけていただければと思います。
・読み聞かせ
上述2.の身体性と、絵本の読み聞かせに大きな関係があります。
読む生活の最初の瞬間は、赤ん坊が大好きな人のひざのうえで、腕に抱かれているところから始まる、とした上で、次のように述べます。
「赤ん坊が初めて言葉を発する前、読むことにまつわる最初の体験の色あせないこの身体的側面が、ごく幼い脳の中で、感じ--触覚と感情--の領域を、注意、知覚、記憶、そして言語の領域と結ぶのです。」
「赤ん坊は人間の声を聞くことと言語系を発達させることとを、驚くほど結びつけているのです。
親が子どもに、子どもだけに向けて、ゆっくり丹念に読み聞かせをするとき、しかも親子が互いに注意を集中させていたら、これらの領域にどれだけもっと多くのことが起こりうるか、考えてみましょう。」
・「深い読み」と民主主義
「書記言語の発明が人類にもたらした最も重要な貢献は、推論にもとづく批判的論法と内省する能力のための民主的土台です。これは集団的良心の基礎です。二一世紀の私たちが、きわめて重要な集団的良心を維持するつもりなら、社会のメンバー全員が、深くかつ上手に読んで考えることができるようにしなくてはなりません。」
・「読む」ための脳回路はひとつではない
本書を読みこなす上で必要な予備知識として1970年代に米国の社会学者マクルーハンが唱えたメディアに関する視座の転換がありそうです。マクルーハンは名著『メディア論』で、情報の中身(コンテンツ)もさることながら、それを伝える媒体(メディア)にも、認識や価値観に影響を与える、つまり世界を変える力があると指摘しました。
「メディアはメッセージである」
実は文字もメディアです。英語圏で読字を習得した人間と、中国語圏、日本語圏で読字を習得した人間とでは、異なる思考回路、思索パターンを身につけている可能性があります。
「脳が本を読む」とき、視覚的に受容した文字を脳内で音に変換しますが、英語圏の音素は40ほど、日本語では10以内でしょう。他方、文字種はアルファベットの26文字に対し、漢字は数万です。日本語では漢字にひらがなが加わります。
すると音の情報から、文字の意味への引き継ぎが行われる際に使う、脳の領域の活性場所あるいは活性の頻度が、英語圏と、中国語圏、日本語圏でかなり違うことになります。つまり、「読む」ための脳回路は、それぞれ異なってきます。「読む」ための脳回路はひとつではないのです。
ここで、この本が一番言いたいこと、印刷ベースの「読み」とデジタルベースの「読み」、ふたつの脳回路をきちんと育てることが、21世紀のデジタル社会において重要関心事項になるはずだと言うポイントへ、つながっていきます。印刷とデジタル両方の読みがもつ最高の特性を自分のものにした、コード・スイッチングするバイリテラシ-脳の形成、これです。
「次世代には、最初からはっきりと異なる読字コードを発達させることが期待されます。次世代はそれらのモードを、自動的に異なる読字目的に展開するのです。たとえば、電子メールのためにはより速い「軽い読み」モードを使い、もっと深刻な素材のためには、おそらくたいていは文章をプリントアウトすることによって、深い読みモードを使うでしょう。」
■お勧め本
・『デジタルで読む脳 X 紙の本で読む脳 :「深い読み」ができるバイリテラシー脳を育てる』
・『失われた時を求めて 1~第一篇「スワン家のほうへI」Kindle版』