夏草が生い茂ってきました。孫と時々遊ぶ近くの公園では生い茂った夏草が孫の背丈を追い越して、どうかすると孫の姿が見えなくなってしまいます。自分の背丈以上の草に囲まれて、私の姿が見えない孫は不安になります。
こんなとき、例えばですがドローンが手元にあって頭の上高く飛ばすことができ、スマホ(ま、孫はスマホをもっていません、あくまで「たとえば」です)で上空からの画像が見れたら、案外すぐそばに私(じいじ)がいることを知り孫は安心でしょうね。
こういう、一つ上から全体を俯瞰する立ち位置のことを学問の世界で「メタ」と呼びます。
■メタという視点:メタ人間学、霊長類学
現代社会は西欧近代の様々な英知のうえに考案された制度や仕組みで成り立っていて、しかし20世紀初頭より次第にそれらの制度や仕組みの矛盾が噴出してきました。20世紀の二回の世界大戦、いまだに止まらない核武装。これら「戦争・暴力」に対しなかなか明快な解決策を見いだせず、最近ではテロが私たち人間社会に不安を広げています。
さてこの「戦争・暴力」を議論するとき私たちは、「戦争・暴力」を人間の性として、また人間社会にやむを得ず付随するものという大前提で、話を始めていないでしょうか。オバマ元大統領の平和記念公園での演説もそうでした。「長い歳月の間に人類の暴力は減少し、今日、私たちは人類が地上に出現して以来、最も平和な時代に住む」ことを実証したとされる書籍、『暴力の人類史』ですらそうです。
トマス・ホッブズの『リヴァイアサン』やジャン・ジャック・ルソーの『人間不平等起源論』の系譜です。
が、メタで見たらどうなのでしょう。メタ人間という視点から見たら、です。
日本出自の学問領域として霊長類学という学問があります。人間と人間社会をを理解するため生物としての人間を考える学問。人間が哺乳類のひとつだという知識は学校で習ったことがあります。その哺乳類のサブカテゴリーとして霊長類があります。いわゆるサルをグルーピングしたカテゴリーが霊長類で、厳密に定義すると人間は哺乳類/霊長目/ヒト科/ヒト属/ホモサピエンス(Homo sapiens)に位置づけられます。人間を他の霊長類の生物と同列の次元に置き比較することで、ヒトより一段と高い立ち位置から人間を探求する、「メタ人間」学、それが霊長類学です。
■ネアンデルタール人はいなくなった
かつてヒト科/ヒト属には多くの仲間がいましたが、いまやヒト属には人間(=Homo sapiens)しかいません。その昔たとえばネアンデルタール人がいましたが彼らは絶滅しました。Homo sapiensが戦争と暴力で絶滅してしまわないよう、「メタ人間」学の研究成果に耳を傾けてみましょう。
人間の進化を現す図表として、四つ足歩行から二足歩行に移行する絵柄がよく取り上げられます。しかし霊長類学の世界でこれは間違いだということが定説になっています。アフリカの熱帯雨林で生まれた人類の祖先は樹上生活をしていました。たまに地上に降り立つこともありましたがその際、どうやらすでに直立していたようです。その後、気候変動などから熱帯雨林の縮減が起きます。このとき霊長類の中で、縮小し点在する熱帯雨林に残留したグループと森を出てサバンナへ出たグループがあり、人間の祖先は後者でしたが、二足歩行で森を出たのでした。
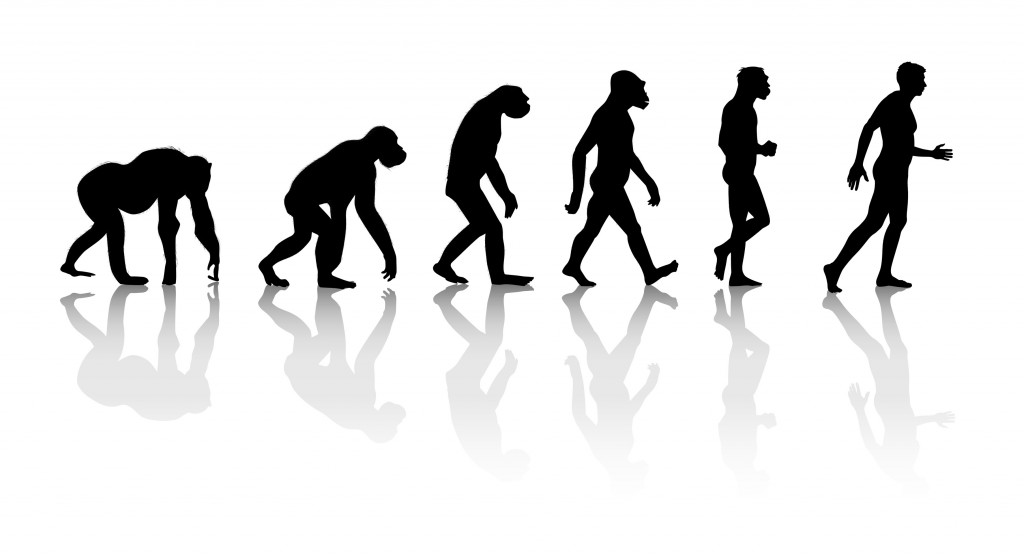
(出典:الانتخاب الطبيعي 自然淘汰 http://bit.ly/2roQkAW )
「メタ人間」学は新しい知見をもたらしてくれます。四つ足から二足歩行へ、ではなかったのですね。
では「戦争・暴力」についてはどんな新しい知見を披露してくれるのでしょう。
■ホモ・サピエンス(Homo sapiens)もいつか、いなくなるのでしょうか
オバマ元大統領は平和記念公園での演説で、「我々のはじめの先祖は火打石から刃物を作ることを学び、木からは槍を作るようになりました。そしてそれを狩りのためだけではなく、自分の仲間に対して使うようになってしまったのです」と言いました。
それは間違いだ、と霊長類学は言います。
まずそもそも人類は狩猟者ではなく、つい最近まで(霊長類学では数万年前が「つい最近」です)肉食獣に狩られる存在だった。二点目として人間に近縁な霊長類が群れを作る理由は、彼らが「狩られる存在」だったことを背景に、食物を効率よく採集するためと、捕食者から身を守るためだった、というのです。『暴力はどこからきたか』で京大総長の山極寿一氏が力説しています。
山極寿一氏はさらに『家族進化論』で、人間が同種の仲間に武器を向けたのは約1万年前に農耕が始まってからの出来事で、人類の進化7百万年の期間中の「つい最近」のことだと言います。定住し、食料生産を始めると「余剰」が生じ、戦士のような生業に関わらない職能人が出てきた。そのことと「戦争」とがリンクしているのです。
つまり戦争が人間の本性などとはとても言えない。
そもそも狩猟と戦争は動機が違います。狩猟は食べるための、生物的な生存のための活動ですが、戦争は相手と合意するための自己主張で、経済的戦略的な選択肢のひとつ。相手が認めてくれれば戦いを続ける必要はないので止む。上下巻合計で千ページを超す大作『暴力の人類史』が扱うのは、90%以上農耕が始まってからの時代で、確かにこの間、経済的な選択肢を倫理や道徳に昇華させ、さらには刑法などを制度化し、「戦争・暴力」を抑止する社会的な仕組みを人間は鍛えげてきました。が、それは農耕が産みだした価値観や世界観、またその上に築かれた人間社会モデルを前提にしたもので、行き詰まりが誰の目にも明らかです。
他方、そうでない別の人間社会モデルがかつてはあったのだし、そればかりか人類史の中で圧倒的にその期間のほうが長いのです。
■ホモ・サピエンス(Homo sapiens)が、この地球からいなくならないために
狩猟採集民としての人類は、自分たちを森の中に埋め込まれた存在と認識していた、その価値観、世界観を森を出た後も長く保持していたのではないか。これに対し、農業活動をする過程で人間は自然を客体化し、自然を人間は、手を加え変える対象として認識しはじめた。その結果「余剰」を起点とする人間社会モデルへの変化が生じたのです。
昨年、2016年、専門誌Natureに「Lethal violence deep in the human lineage」というタイトルの論文が掲載されました。種の中で、暴力によって死亡した割合が系統的にどう変化したかを調査した結果を発表したものです。その数値は哺乳類全体より霊長類は高く、しかし霊長類の中で人間の祖先にあたる類人猿では低い、という結果でした。
この結果を山極氏は、霊長類で上がったのは集団が連合を組むようになり、集団間、また集団をまとめるため集団内で種内の争いが増えた。これに対し、類人猿は「力による階層性ではなく、平等な意識に基づいて争いを避けるようなルールができたから」と分析しています(「「人類史」のその先へ」 『現代思想』2017年6月号所収)。
「狩猟採集民はある特徴を持った社会性を維持してきた。徹底的な分配と交換を通じた社会関係と、権威を抑える仕組みである。
(略)だれも(大きな獲物を獲った[筆者註])狩人に対する賞賛の言葉を口にしない。これは大きな成果をあげたことによって、特定の個人に権威や嫉妬が集中するのを防ぐためである。
(略)狩猟採集民の分配は、相手からの見返りを期待してはいない。(略)狩猟採集民の分配を再考した弘前大学の丹波正は、「分け与える」というより「分かち合う」という表現の方が彼らの平等社会の実態にあっているという。狩猟採集民は所有をできるだけ認めず、すべてを「分かち合う」ことを原則とした社会を営んでいる。所有がなければ「与える」者も行為も生じないのだ。」(『家族進化論』第六章・第六節 分かち合う社会)
では、「戦争・暴力」はどこから来たのか。
『21世紀の資本』が大きくクローズアップさせた、余剰としての富(資本)の「所有」が格差を拡大させ、階級を固定化、権威主義を産み出したとする問題指摘がありました。格差拡大がその時代の社会を不安定化させ、格差ゆえの不満、不平が不安定化した社会に乗じて、内にあっては時の権威へ歯向かう行動へ向かわせ、外に対しては格差解消(=内側の課題)のため外の富を取りに行く、「所有」増長を目指す。そういう「戦争・暴力」の負の連鎖を生んでいるのかもしれませんね。
「所有」概念とそれを支える制度の見直し、人間社会の未来へ向けた刷新、再定義が必要なのでしょう。
いずれにせよ、「暴力が人間の本能だとすると、戦争は不可避の運命にある」といった考え方は的外れだと言えるのではないでしょうか。
だからといって狩猟採集民の社会モデルへ戻ることはできないでしょう。しかし現状変革のヒントは見出せるかもしれません。知恵の出しどころです。ネアンデルタール人とは違う道をゆきたいものです。そのためには私たちも勉強しなくてはいけませんね。
実は三月から「iCardbook」という新レーベルでカード型専門書ebookを展開中ですが、そのラインナップのひとつとして、この霊長類学の成果を上下本、200枚の知識カードで物語に編成した作品を企画しています。今年の秋くらいの発刊を目指し現在作業中です。どうぞご期待ください。
『人類の社会性の進化(山極寿一・本郷峻)』
(下)共感社会と家族の過去、現在、未来














