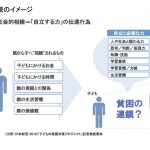◎ラス・カサスは、「人類はひとつ」を押し立てて、16世紀、スペインによる、征服戦争を背景にした新大陸(インディオス)先住民に対する強引な改宗や迫害を告発したドミニコ会士。平和的改宗計画と先住民の人権擁護をスペイン国王に訴え、「インディオス新法」を発布させた(1542年)◎
目次
1.スペインの征服戦争とポルトガルの交易競争
2.キリスト教世界の価値観の普遍性が試される
3.ラス・カサスとビトリアの「普遍性」
4.21世紀の「普遍性」論へつながるセプルベダとラス・カサスの論争
1.スペインの征服戦争とポルトガルの交易競争
ヨーロッパ諸国家による非ヨーロッパ地域の植民地化

(ストラボン - Definición y sinónimos de Strabon en el diccionario japonés https://educalingo.com/es/dic-ja/sutorahon )
ヨーロッパの西端、イベリア半島には8世紀、イスラーム教徒が侵入し、以来約800年間イスラーム支配体制が確立、イスラーム文化の華が咲きました。そのなかでアラビア語に翻訳されていたギリシア学が、この地でラテン語に再訳されてキリスト教世界に浸透していくという、後のルネサンスの下地が準備されてもいたのでした。
そしてその中には紀元前5世紀にピタゴラス学派の主張した世界球形説の紹介や、アレクサンドリアの図書館長エラトステネスの投影図法による最初の世界図、新大陸が予言されている前1世紀のストラボン『地理学』の世界図などがありました。
さてこれに対しキリスト教諸国王は国土を回復(レコンキスタ)すべく奔走します。貴族や教会に政治・経済上の特権を与え、あるいは農民には土地、移住特許状を、さらに都市には特権保障の特許状を与えるなど戦闘力増強に邁進しました。
この過程でエンコミエンダ制が生まれました。それは、キリスト教徒の騎士団がイスラーム教徒の土地を征服すると、個人に対し、異教徒から奪った土地を一時的に下賜する制度でした。すなわち、エンコミエンダ制とは、キリスト教化を条件に現地人労働力を実質的な奴隷として使役することを可能にした農園経営形態のことです。
そして最終、半島に群雄割拠していた諸侯のなかからカスティリャとアラゴンが合併、統一国家スペインを出現させついに1492年、イスラーム最後の拠点グラナダを陥落させました。
このレコンキスタ(国土回復戦争)の余勢をかって出てきたムーブメントが、ヨーロッパ諸国家による非ヨーロッパ地域の植民地化の活動でした。
それまでイベリア半島経由入ってくる絹、陶器、香料、その他の東洋物産を、イスラーム商人の手を経ずに直接手に入れること、あるいは直接東洋に達する道を発見することなどを目的として、世界が球体であるとの予備知識をもとに、東方への探検航海が試みられたのです。またマルコ・ポーロの『世界の記述(東方見聞録)』の東洋に関する記述への関心や、造船技術と羅針盤などの航海技術がイスラームから伝わったことも、動機のひとつに数えられます。
新大陸の発見とスペインの征服戦争
東方への探検航海はポルトガルが先行しました。そこでスペインはクリストファー・コロンブスに、グラナダが陥落した1492年、西航することでインドを目指す計画を許可、結果、アメリカ大陸が「発見」されました。
ところがコロンブスは第1回航海の帰途、出港地スペインのパロス港をめざしましたが嵐に遭い、リスボンに緊急入港したのです。そのためコロンブスの発見はポルトガル王ジョアン2世の知るところとなりました。その結果コロンブスがインディアス(新大陸であったが彼はインドの一部と主張していた)に到達した直後から、スペインとポルトガルの勢力圏をめぐる対立が表面化します。
スペインとポルトガルはいずれもローマカトリックを国教としていたので、ともにローマ教皇による裁定にすがろうとしました。
1494年にローマ教皇の仲裁によってスペインとポルトガルの間にトルデシリャス条約が結ばれ、スペインは「新大陸」における征服の優先権を認められました。条約では新たに征服される土地と住民はスペイン国王に属すこととされ、スペイン国王の代行者たるパシフィカドール(鎮定者)は、先住民を服従させるか鎮定する権能を担ったのです。このため、スペイン人が先住民に出会った際に、先住民に対しての選択肢は征服以外になくなり、このことが交易の可能性があったポルトガルやイギリス、フランスによるアメリカ大陸の征服とスペインのそれとを大きく異なるものへと導いていきました。
2.キリスト教世界の価値観の普遍性が試される

(El Tratado de Tordesillas - ¡RESUMEN CORTO! https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/tratado-de-tordesillas-resumen-3743.html )
教皇至上権と教化活動の顛末
先述のトルデシリャス条約はローマ教皇の「贈与大教書」を下敷きにしていました。
スペインに生まれ、イタリアのボローニャ大学で法学を学んだローマ教皇アレクサンデル6世(在位1492~1503)は教皇領の拡張を志向、1492年、新発見の地に対するスペインの権利を布教権という形で認める、という「贈与大教書」を発布します。これにはスペイン王に対し領有権を持つことを承認するが、それは原住民に対しキリスト教を布教する義務とのひきかえだよという含意がありました。
するとスペイン王はこの「贈与大教書」を、スペイン国王によるインディアス支配の正当化根拠とし、それを拒否するインディオに対する征服戦争は正当なものだと主張することになったのです。思想的に、ローマ教皇を全世界の霊的・世俗的支配者と見る教皇至上権の概念が、この主張の背景にありました。
そして1503年、新大陸インディアスにエンコミエンダ制が導入されます。
しかし時間が経過し、インディオのキリスト教化は名ばかりであることが多くの宣教師たちの知ることとなります。殺戮と酷使による死亡という、残虐な実態です。スペイン人による征服戦争(殺戮)と、エンコミンダ制のもとでの労働(酷使)により大勢のインディオが死亡しました。そしてその労働力を補うための近隣の島々への奴隷狩りが盛んに行われます。しかし、連行されたインディオ奴隷も、結局は同じようにスペイン人の虐待・酷使によって死に絶えたのです。
ローマ教皇より「新世界」の先住民のキリスト教化を委託されたスペイン国王、その国王に代わって、実際に布教・改宗化活動に従事した宣教師たち(特にドミニコ会士)は、インディオ擁護の声をあげました。そして、
1.スペイン国王にあるインディアス領有・支配の正当性
2.征服戦争の正当性
3.エンコミエンダ制の合法性
4.人間としてのインディオの権利
と言う4点に絞って当時の通念に疑問を投げかけたのでした。1511年のできごとです。
こういった潮流を背景に1512年には、国土回復戦争(レコンキスタ)の伝説的英雄エル・シッドの故郷、ブルゴスの名を冠した法律が制定されました。先住民への虐待を禁じたブルゴス法です。ただブルゴス法はエンコミエンダ制の合法性は認めており、あくまでその中でインディオの保護と教化に重点を置き、労役義務を制限することを目的として制定されたものでした。
こうして16世紀のヨーロッパ・キリスト教世界の伝統的な価値観や世界観の、普遍性が問われることとなっていくのです。
3.ラス・カサスとビトリアの「普遍性」

(Bartolome de Las Casas | Biography, Books, Quotes, Significance, & Facts | Britannica https://www.britannica.com/biography/Bartolome-de-Las-Casas )
ラス・カサスの「普遍性」論の特徴
スペインのセビリアに生まれたバルトロメ・デ・ラス・カサスは、1502年、インディアスへ渡航(18歳)、エンコミエンダの運営者の一人として働きます。このときはまだ聖職についてはいません。その後、1514年に回心を経験し(30歳)自らのもとにいたインディオを解放し、ここから大陸の先住民インディオの人間性を尊重するための活動を始めます。1521年にはドミニコ会に入会し(37歳)、聖職者となりました。
活動はふたつあり、平和的植民化運動(軍人でなく宣教師のみで行う改宗化活動)と、インディアスの実情を報告し、インディアス統治の抜本的な改革を訴える宮廷活動(そのための著作も)です。後者については、征服戦争の即時中止、エンコミエンダ制の撤廃とインディオ奴隷化の全面的禁止を求めたのです。インディオも我々スペイン人と同じ人間だという考え方をその論拠としていました。
この当時スペイン宮廷に、喫緊の課題である「インディオ問題」について、二人の論客がいました。スペイン・サラマンカ大学神学部教授フランシスコ・デ・ビトリア、スペインの神学者・哲学者フアン・ヒネス・デ・セプルベダの二人です。ただこの二人が、インディオス事情について文献からの知識だけを頼りに持論を展開したのに比べ、ラス・カサスは自身の現地実体験が元になっている点が特徴です。彼は征服戦争の実態とエンコミエンダ制の弊害を知り尽くしていたのでした。「人間としてのインディオ」の視点がラス・カサスの「普遍性」議論に異彩を施したゆえんです。ドミニコ会入会以降古典籍への造詣を深めたラス・カサスは、宮廷においてインディアス事情に通じたた重要な人物として発言力を強めていくのです。(ちなみにセプルベダが依拠した情報の中にはコルテスからものもあり、コルテスの征服事業を顕彰した書籍も残しています)
「大教書(サブリミス・デウス)」と「インディアス新法」
新大陸での植民者たちの目にあまる行為とインディオへの虐待を問題視する意見があることに対し、1524年スペインではインディアス評議会が設けられていました。評議会はその後、王の直属機関、枢機会議に格上げされます。その評議会・枢機会議に対しラス・カサスはしきりに書簡を送り、現状を報告、同時に現地にてインディオへの平和的布教に取り組んでいました。
こういったラス・カサスの地道な啓蒙活動はヨーロッパにおいて徐々に評価され、「大教書(1537年)」、「インディアス新法(1542年)」となってその成果が現れたといえます。
1537年に教皇パウルス3世は「大教書(サブリミス・デウス:Sublimis Deus)」を交付します。それはアメリカ先住民が、たとえ異教徒であっても、自由や私有財産の権利を持つ完全に理性的な人間であるという内容で、征服戦争ではなく平和的改宗化策を推奨するものでした。
他方、1542年にスペイン王カルロス1世(そのときは神聖ローマ皇帝カール5世にもなっていた)が、「インディアス新法」を制定します。
「インディアス新法」は被征服者(インディオ)の擁護を主眼としていて、歴史上数ある植民法の中でも、キリスト教的人道主義精神にあふれた希有な植民法典と評価されています。
その証拠に「インディアス新法」はその正式名称を「インディアスの統治並びにインディオに対する正しい扱いとその保護を目的として、国王陛下が新しく制定された法令及び命令」というものです。そして第7条には「インディオが自由な人間であることを明記し、インディアス枢機会議に対しインディオの保護と繁栄に最新の注意を払うことを命じた」と記してあります。
しかし同時に「インディアス新法」は、カルロス1世の対ヨーロッパ政策の遂行に必要な財源の源泉としてのインディアスの必要性に鑑みて、ラス・カサスの改革案を部分的に受け入れて編纂した植民法であるという側面もありました。
それというのも、当時ビトリアの講義が人々の話題となっていたからです。講義は教皇至上権を否定していました。教皇至上権と「贈与大教書」を自らのインディオ政策、対ヨーロッパ政策のよりどころとしていたスペイン王カルロス1世にとって特別講義は脅威だったのです。
ビトリアの特別講義
ビトリアはピサロによるインカ皇帝殺害(1533年)の報に接すると征服戦争の正当性に疑義をいだき、1539年、サラマンカ大学の特別講義において「インディオについて」および「戦争の法について」を講じました。
サラマンカ大学神学部教授ビトリアは一冊の著書も書いていません。ところが特別講義だけは、死後編纂され、『神学特別講義』として1557年に出版されています。彼が教皇至上権を否定していたからです。
ビトリアはトマス・アキナスの「神の法は自然の理性に基づく人定の法を無効としない」と言う理論に依拠。それを踏まえ、ローマ教皇の教権と俗権とを区別し、教皇は全世界の支配者ではないと主張したのです。そして仮に、教皇が全世界に対して世俗的支配権を有しているとしても、その権力を世俗の君主に委ねる事はできず、ただ霊的な事柄に関して特権を持つだけであるとし、「したがって、たとえ異邦人たちが教皇の支配権をいっさい承認しようと欲しないとしても、だからといってそのことだけで、教皇は彼らに戦争を仕掛け、その財産を奪うことはできない」と結論しました。
彼は、ローマ教皇アレクサンデル6世の「贈与大教書(1492年)」はスペイン国王にインディアスにおける世俗統治権を委ねたものではないと断定、また、1537年のローマ教皇パウルス3世の「大教書(サブリミス・デウス)」に対してもその撤収を求めたのです。
他方国際法を国家の法の上位に位置づけ、独自の「万民法理論」を構築、新しく、スペイン人による征服戦争を正当化する場合を限定列挙してみせ、これをスペイン王の征服戦争・正当性の根拠とすべしとしたのです。
通底するのは普遍的人類社会とその社会に共通の法という概念です。
つまり、人間は人間であるという共通の本性によって普遍的な人類社会を構成する。その社会にはすべての人間に当てはまる共通の法が支配し、その法によって人間はだれでも人間としての基本的な権利が保障されていなければならない。
それゆえ、スペイン人がインディオに対して行う戦争も、その普遍的人類社会に共通な法によって規律されるべきであり、彼らが異教徒であるとか野蛮人であるなどといった理由から、非道な扱いを受けるべきでない、としたのです。
ここで、ラス・カサスが教皇至上権論を肯定し、他方ビトリアは教皇至上権論を否定していたのですが、両者ともに、「普遍性」を主張するその礎に「人類はひとつ」という考え方を持ち込んだ点が共通しています。西欧近代が確立する以前に産まれたこのコンセプトはしかし、国民国家の枠組みが成熟していくに連れ、思想界からはフェードアウトしていったのがその後の歴史の実相です。
そしてここに、ほかならぬスペインの文化的優秀性を自説の「普遍性」の拠り所にしながら、征服戦争の正当性を奉じる論者が登場します。フアン・ヒネス・デ・セプルベダです。
4.21世紀の「普遍性」論へつながるセプルベダとラス・カサスの論争
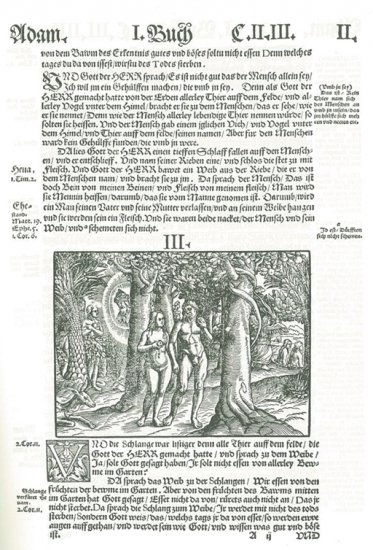
(1545年に発行されたルター訳ドイツ語聖書の復刻版 https://biblehouse.jp/?pid=43966903 )
「目的は手段を正当化しない」がラス・カサスの主張
「スペイン語は神と話す言葉だ」。カルロス1世の言葉です。
1516年スペイン王となったカルロス1世は1519年、スペイン生まれのスペイン育ちであったものの、中欧の神聖ローマ皇帝カール5世(在位1519~1556年)となり、以降キリスト教圏の防衛と拡張に腐心する生涯を送りました。
このころキリスト教圏防衛の必要性は、外側だけでなく内側にもありました。ルターの福音主義運動に端を発した「宗教改革」により西方のキリスト教界の統一が大きく揺らいでいたのです。宗教改革の背景にはヨーロッパ諸侯が教会勢力に対抗するだけの力を蓄わえてきたこと、そして15 世紀に登場した活版印刷機の普及による広範な民衆教化の成功(ドイツ語で書かれた「ルター聖書」は前例のないほど短期間のうちに全ドイツに広まった)などがあります。
カルロス1世はイタリアの支配権をめぐりフランス、オスマン帝国と戦いました(イタリア戦争)。さらにドイツ領内には宗教改革運動が吹き荒れ、一旦オスマン帝国の侵入への防御などのためにルター派の布教を許可するもふたたび禁止するなど、対ヨーロッパ政策に苦慮しました。
カルロス1世にとって新大陸への進出は、キリスト教圏の拡張であり、同時にそれはフランス対策、オスマン対策、宗教改革運動対策のための原資、とりわけ戦費を得る活動でもあり、その正当性についてキリスト教的に揺るぎのない根拠を必要していたのでした。
この「揺るぎのない根拠」について、ビトリアはキリスト教義を離れ、「万民法」をよりどころにしたのに対し、ラス・カサスはあくまでキリスト教的理路を提示しました。
つまりラス・カサスは「贈与大教書」を、インディアスにおけるスペインの存在を正当化する唯一の権限と認める一方、目的は手段を正当化しないという原則に立って、スペイン国王によるインディアス支配はローマ教皇より委ねられたインディオのキリスト教化の手段に過ぎないと論じ、キリスト教化のための征服戦争を否定しその即時中止を訴えました。
目的は手段を正当化しない。
「善が生じるために、悪がなされてはならない(聖パウロ 「ローマの信徒への手紙」(第3章))」のです。
セプルベダとは
しかしセプルベダは「目的が手段を正当化する」という論者でした。
フアン・ヒネス・デ・セプルベダはスペインの裕福なキリスト教徒の家に生まれました。イタリアで論理学、哲学を修め、ポリーニャ神学校にて神学を学び、アリストレスの翻訳者・注釈者として名声を博した彼は、1523年からローマにある教皇庁の公式翻訳官としてアリストテレスの作品の翻訳作業に従事していました。
セプルベダの主義主張の動機に、スペイン王カルロス1世(皇帝カール5世)による「ローマ略奪」があります。
「ローマ略奪」とは1527年5月、神聖ローマ皇帝カール5世(スペイン王カルロス1世)の軍勢がイタリアに侵攻し、教皇領のローマで殺戮、破壊、強奪、強姦などを行った事件のことです。東方でのオスマン帝国のウィーン包囲(第1次)の危機が迫るなか、皇帝のもとに、ローマ教皇がフランスと結託したとの情報が寄せられ、それへの応答としてローマ侵攻を決意します。スペイン兵、イタリア兵などからなる皇帝軍とドイツの傭兵がローマに進軍しましたが、その傭兵・ドイツ兵にはカトリックを憎むルター派が多かったといい、指揮官ブルボン将軍が戦死、統制がとれずに暴徒化し、略奪行為に走ったと言われています。

ローマの略奪(akg-images - Sacco di Roma https://www.akg-images.com/archive/Sacco-di-Roma-2UMDHUSWIVE5.html )
セプルベダはこのときローマにいました。
そこで「ローマ略奪」にオスマン帝国やルター派、つまり異端者たちからの脅威にもだえる、キリスト教世界の混乱と危機を感じ取ったのです。そして彼は、宗教改革の嵐の中、キリスト教諸国の中でも特にスペインが、ローマ教会の守り手として戦う姿に感銘、征服戦争はインディオの改宗化(キリスト教世界の拡大)を容易にするために、スペイン人が遂行している「聖戦」であるとの論理を構築します。目的(キリスト教世界の拡大)は手段(聖戦)を正当化する。それに異を唱えるのは異端的行為だと考えるようになったのです。
したがって他でもないスペイン人の中に征服戦争の正当性に疑義を挟み、その中止を求めている人たちが存在することには憤りをすら感じました。1542年皇太子フエリペの教育係としてスペインへ帰国するとセプルベダは、長年研鑽を積んだアリストテレス哲学を武器に、理論的に征服戦争の正当性を明らかにし、論争に終止符を打とうと考え、『第二のデモクラテス』書き綴ったのでした。
バリャドリッド論争
もともとセプルベダは征服戦争の問題すなわち戦争の法的問題を扱った論策を二編、著していました。ひとつは、1529年、オスマン帝国のハンガリー進出とウィーン包囲を契機に、異教徒に対する戦争の必要を訴えた『対トルコ戦のすすめ』。今ひとつは、1531年に、オスマン帝国との戦争を不正とみなすルター派の理論に反論し、軍事活動がキリスト教と矛盾しないことを立証するために著した対話体の作品『第一のデモクラテス』(1535年ローマで出版。1541年スペイン語訳がシベリアで出版)です。
それで『第二のデモクラテス』は、インディオの文化的能力を否定し、キリスト教的自然法という普遍性のある理論に照らし征服戦争は聖戦であると論じる内容となりました。
この『第二のデモクラテス』の印刷許可が願い出られていることを知った、ビトリア理論を継承する神学者たちは、異議を唱えました。そこでカルロス1世は征服事業を一旦中断した上で、正当な征服戦争のあり方と先住民のキリスト教化方法について審議するよう命じます。そして宮廷においてインディアス事情に通じた重要な人物として発言力を強めていたラス・カサスにも審議への参加を要請しました。
審議は1550年8月15日にバリャドリッドで開会され、ここに召喚されたラス・カサスとセプルベダの2人の論者が代わる代わる自分の意見を陳述するかたちで進行しました。審議会は、インディオ(インディアス先住民)問題について明確な決着を下さなかったものの、『第2のデモクラテス』の刊行は却下されました。
ところでセプルベダのインディアス論は、スペインの文化的優秀性という視点に大きく依拠していました。
その証拠に、対話体の作品『第二のデモクラテテス』で、ルター派の異端者レオポルドに、「なぜスペイン人以外のキリスト教国民はインディオを支配できないのか」と問わせ、デモクラテスにこう答えさせています、「(思慮分別、徳、宗教の面で)スペインと肩を並べられるような国はほとんどありません」。
またこの立論を成立させんがために、結局のところ自然法の普遍性を否定してもいました。すなわち一方でトマス・アキナスを引用し、自然法とは、神の法が理性を付与された被造物(人間)に入り込んだものと言う伝統的な自然法理論の立場に立ちながら、他方自然法の規範を決定するのは博学かつ有徳で思慮深い人々であると主張していたからです。すなわち自然法は、理性にかける自然奴隷とみなしたインディアには適用されないとしたのです。
不完全なもの、邪悪なもの(=インディオ)が、より完全なもの、正しいもの(=キリスト教徒とくにスペイン人)に従うのは「自然法」に合致したことであるとしました。
この点において、のちに国民国家時代の戦争を正当化する論拠を準備した人物とも想定でき、逆にラス・カサスやビトリアの「人類はひとつ」という考え方によって立つ「普遍性」議論には、先進性がうかがえる、ともいえるのではないでしょうか。
目的は手段を正当化するか。遅れている人は進んだ人に従うべきか。
21世紀のこんにち、20世紀までの「戦争」は、「経済制裁」や「内戦への介入」という形式に姿を変えています。「自由や人権は人間の及ばない自然法によってつくられたものであり、絶対的な価値を持つ」との考え方から、西洋近代の成果物である自由や民主主義を世界に広めるのが先進国の使命であり、このような道を選択しない、受け容れないのは間違いである、という主張が導き出され、それが他国への「経済制裁」や「内戦への介入」の正当化理由として選択されています。
これは16世紀のキリスト教化と征服戦争あるいはエンコミンダ制と、ある意味パラレルなことが起きているといえないでしょうか。
セプルベダの主張が姿を変え、よみがえっているともいえます。目的は手段を正当化するか。どういう範囲でなら。21世紀への読み替えが必要としても、ラス・カサスやビトリアの理路は、21世紀の私たちに参考になるのかもしれません。
■参考文献
『インディアスの破壊についての簡潔な報告』
『インディアス文明誌』(『インディオは人間か (アンソロジー新世界の挑戦 (8))』に収載)
『第二のデモクラテス』
『ヨーロッパ的普遍主義』