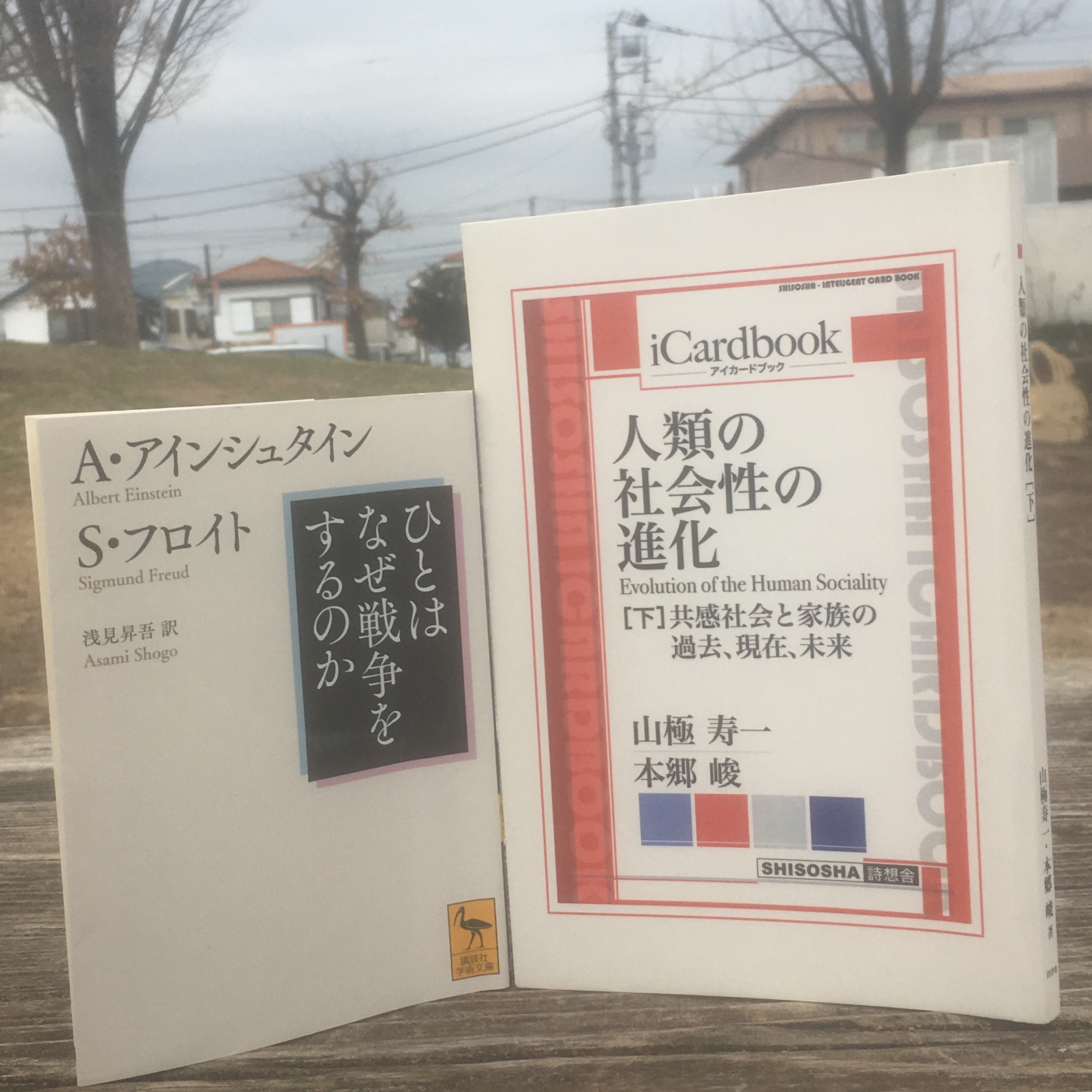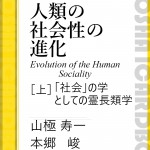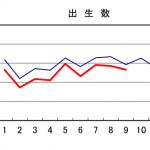前の記事に、解剖学者の養老孟司氏が解説した本に触れました。その本のタイトルは、『ひとはなぜ戦争をするのか(講談社学術文庫)』。
およそ百年前の1920年1月、史上初の国際平和機構である国際連盟が設立されました。第一次世界大戦が、それまでの100年間のすべての戦争における軍人の死者数を遥かに超える痛ましい戦争であったことを契機に、大規模な常設の国際平和維持機構の必要性が痛感されたのでした。
提案したアメリカがそもそも参加しないなどの事情はあったものの、国際連盟発足後の1920年代は比較的安定した時期として推移しました。ところが1929年、ニューヨークのウォール街における株の大暴落を端緒とする世界経済恐慌が、資本主義諸国を直撃し、国際的協調体制が不安定化していきます。
そういった時代背景の中、1932年、著名な科学者に対し国際連盟は、人間にとってもっとも大事だと思われるテーマを取り上げ、もっとも意見を交換したい相手と書簡を交わすという企画を持ちかけました。彼は即座に応答し、意見交換の相手に精神科医で深層心理学を確立したジグムント・フロイトを、そしてテーマに「戦争」を掲げたのです。科学者の名は、アルバート・アインシュタイン。
この往復書簡をまとめたのが、『ひとはなぜ戦争をするのか(講談社学術文庫)』なのです。
■アインシュタインの問い(1932年7月30日付けフロイトへの書簡)
「人間を戦争というくびきから解き放つため、いま何ができるのか?」
これが私の選んだテーマです。
アインシュタインは、「国際的な平和を実現しようとすれば、各国が主権の一部を完全に放棄し、その活動に一定の枠をはめ」る以外にないとしたうえで、しかしこれは実現が難しいと認めます。
そのうえで、人間の心の問題に「解」をみつけられないかと考えたのでした。
「人間には本能的な欲求が潜んでいる。憎悪に駆られ、相手を絶滅させようとする欲求が!
(中略)
ここで最後の問いが投げかけられることになります。
人間の心を特定の方向に導き、憎悪と破壊という心の病に冒されないようにすることはできるのか?」
■フロイトの答え(1932年9月 アインシュタイン宛の書簡)
分量にしてアインシュタインの四倍の手紙を、フロイトは返します。
まずアインシュタインの最初の「解」、国際連盟のような機関が、国際的な利害の対立に対し裁定を下す方法が正しい道だとした上で、ただしそれは、裁定を押し通すだけの「力」を国際連盟が持つことが必要で、そのためには、個々の国々が自らの権力の一部を返上することが条件になってくるため、アインシュタイが言うように、確かに現実的でない、と追認します。
そして精神分析上の概念、「欲動」の理論を紹介しはじめます。人間は生の欲動と死の欲動の両方を併せ持つ生物なのです。
ちなみに講談社学術文庫には、養老孟司氏の解説文と共に、精神科医・斎藤環氏の解説があり、それによると、「欲動」とは精神分析学で、人間を行動へと駆り立てる無意識の衝動、しかも「心よりもむしろ身体に深く根ざしたある種の傾向、ベクトル」のことで、本能とは区別されます。人間に本能はないのです。たとえば生殖。動物は一般に特に教わらなくても、遺伝子に刻まれたプログラム(本能)で生殖を行います。ところが人間は後天的に教わることがないと、生殖を行うことができません。
さてフロイトに戻ります。
人間の生を、保持し統一しようとする欲動が生の欲動で、生を破壊しよう、攻撃しようとするのが死の欲動です。そしてフロイトは、このふたつの欲動は対立物であるより前に、生命の現象、表裏一体の精神活動だというのです。
だから、「人間から攻撃的な性質を取り除くなど、できそうにもない!」。
では、ヒトと戦争、これは避けることができない組み合わせなのか。いや必ずしもそうではない、というのがフロイトの回答です。
「ともあれ、あなたもご指摘の通り、人間の攻撃性を完全に取り除くことが問題なのではありません。人間の攻撃性を戦争という形で発揮させなければよいのです。戦争とは別のはけ口を見つけてやればよいのです。
ですから、戦争を克服する間接的な方法が求められることになります。(略)人間がすぐに戦火を交えてしまうのが破壊欲動のなわざせる業だとしたら、その反対の欲動、つまりエロスを呼び覚ませばよいことになります。だから、人と人の間の感情と心の絆を作り上げるものは、すべて戦争を阻むはずなのです。」
そしてこの「解」が現実味を帯びるのには、「文化」の力が欠かせない、と続けます。
一度起きてしまった戦争を止めさせる、これは至難の業です。ウクライナで起きていることを考えれば察しがつきます。しかし、戦争を起こさせない回路はあるはずだ、それが、フロイトのいう「文化」の力です。
人間の歴史を振り返ればすぐにわかるでしょう。「文化の発展が人間の心のあり方に変化を引き起こすことは明らかで、誰もがすぐに気づくところです。(人間のこれまでの歴史において)ストレートな本能的な欲望に導かれることが少なくなり、本能的な欲望の度合いが弱まってきました。私たちの祖先なら強く興奮を覚えたもの、心地よかったものも、いまの時代の人間には興味を引かないもの、耐え難いものになってしまっています。」
「文化の発展を促せば、戦争の終焉に向けて向けて歩み出すことができる! 」
そう、フロイトは自身の手紙を結びました。
ところで、この「戦争を起こさせない回路」の工夫をヒトが積みあげてきたことは、霊長類学が万年の単位で明らかにしてきたことでもあります。
■霊長類学からの示唆
第二十六代京都大学総長の山極寿一氏が、霊長類学がたどり着いた成果をコンパクトに紹介しています。『人類の社会性の進化(Evolution of the Human Sociality)』。
この中には、たとえば、「第五章 暴力と社会」や、「第八章 家族の変容とヒト社会の未来/第3節 社会の拡大と暴力の起源」といった見出しがあります。
社会システムをアップデートし続けることではじめて存在しえている種、ヒトの、これまでの長い道のり(社会性の進化)の中に、「ヒトと戦争」が整理され、読者の思索を誘います。
戦争や暴力がどうしても人間社会と切り離せないと考えてしまうのは、所有という概念が生まれはじめた一万年前ほどからの発想に、私たちがしばられているからなのかもしれないのです。定住と農耕牧畜とが人間社会のデフォルトになりはじめた一万年前ほどから、それ以前のヒトの、「戦争を起こさせない回路」の知恵、工夫が忘れ去られた結果なのかもしれないのです。
「狩猟採集と農耕・牧畜の大きな違いは必要な土地の大きさと人口密度である。熱帯雨林の焼畑農耕民は狩猟採集民の40分の1の土地で必要な食料を賄えるし、牧畜民はとても狩猟採集が行えないような砂漠やツンドラでも暮らすことができる。また、食料の蓄積ができる農耕民は狩猟採集民の数百倍の人口を抱えることができる。
しかし、定住生活と人口増大、専門家集団、富裕層の出現は、しだいに土地の権利と富を守る武力集団の形成を促進し、集団間の暴力が顕在化することになった。」
この本の下巻の副題は「共感社会と家族の過去、現在、未来」です。「ヒトと戦争」の迷路を解く鍵は家族がはぐくむコミュニケーション能力の知恵にある、という風に読むこともできるでしょうか。つまりフロイトのいう「人と人の間の感情と心の絆」のアップデートや「文化の発展」とは、人類の社会性の進化のひとつの側面と読み替えられそうです。
最後にもう一度養老孟司氏に登場いただきましょう。冒頭の解説文にはこうあります。
「結論というほどのものはない。しかしヒトと戦争という課題は、社会システムの成立と維持の一面と見なすべきであろう。
その社会システムは、右に述べたように、自然発生的なものから、アルゴリズム的なものへと変化しつつある。つまり脳機能としての意識が優先しつつある。個人でいえば意識と身体、集団でいえばアルゴリズム的な社会と自然発生的な社会、その両者のバランスの上に将来の社会システムが構築されていく。戦争の地位も、そのなかで定まるというのが私の予想である。」
「家族は人間のもっとも古い文化的な装置である(山極寿一)